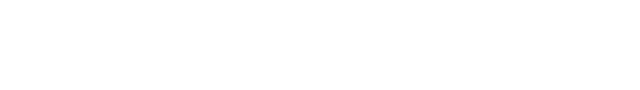逆流性食道炎
逆流性食道炎とは?
胃の中には、食べ物を消化するために非常に強い酸性の「胃酸」があります。
通常、胃と食道の間には「下部食道括約筋」という筋肉があり、胃酸が食道に逆流しないようにフタの役割をしています。
しかし、この下部食道括約筋の働きが弱まったり、胃酸が過剰に分泌されたりすると、胃酸が食道へと逆流してしまいます。
食道の粘膜は胃酸に対する防御機能が弱いため、逆流した胃酸にさらされることで炎症を起こし、様々な症状が現れるのです。
これが逆流性食道炎です。
こんな症状に心当たりはありませんか?逆流性食道炎の主なサイン
逆流性食道炎の症状は多岐にわたります。
いくつか当てはまるものがあれば、一度専門医に相談することをおすすめします。
- 胸やけ:みぞおちから胸にかけて、焼けるような熱い感覚があります。
特に食後や前かがみになった時に強くなることがあります。 - 呑酸(どんさん):胃から酸っぱい液体や苦い液体が口まで上がってくる感覚です。
- げっぷ:食後によくげっぷが出たり、一度出ると止まらなくなったりします。
- 胸のつかえ感・異物感:食べ物が喉や胸につかえるような感じがします。
- 咳・喘息のような症状:胃酸が喉や気管に刺激を与え、慢性的な咳や喘息のような症状を引き起こすことがあります。
- 声のかすれ・喉の痛み:胃酸が喉頭を刺激し、声がかすれたり、喉に炎症が起きたりすることがあります。
- のどの違和感:のどに何か張り付いているような感じや、イガイガする感じがします。
- 胃もたれ・膨満感:胃の不快感や重たい感じが続くことがあります。
これらの症状は、日常生活に大きな影響を与えるだけでなく、他の重篤な病気が隠れている可能性もあります。
自己判断せず、専門医による正確な診断が重要です。
なぜ逆流性食道炎になるの?
逆流性食道炎の原因は一つではありませんが、多くの場合、日々の生活習慣が深く関わっています。
- 食生活の乱れ:
- 脂肪分の多い食事:胃酸の分泌を促し、消化に時間がかかります。
- 食べ過ぎ、早食い:胃に負担がかかり、胃酸が逆流しやすくなります。
- 柑橘類、香辛料、チョコレート、コーヒー、アルコール:食道を刺激したり、下部食道括約筋を緩めたりする作用があります。
- 就寝前の食事:寝ている間に胃酸が逆流しやすくなります。
- 肥満:お腹周りの脂肪が増えると、腹圧が高まり、胃が圧迫されて胃酸が逆流しやすくなります。
- 喫煙:唾液の分泌を減らし、下部食道括約筋を緩める作用があります。
- ストレス:自律神経の乱れにより、胃酸の分泌や食道の動きに影響を与えることがあります。
- 加齢:加齢とともに下部食道括約筋の機能が低下することがあります。
- 姿勢:猫背や前かがみの姿勢は、腹圧を高め、胃を圧迫することがあります。
- 特定の薬剤:一部の薬剤が、逆流性食道炎の症状を悪化させる場合があります。
これらの原因に心当たりがある方は、生活習慣の改善が症状緩和への第一歩となります。
専門医による診断の重要性
「逆流性食道炎かな?」と思っても、自己判断で市販薬を使い続けるのは危険です。
なぜなら、症状が似ていても、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには食道がんなど、より重い病気が隠れている可能性があるからです。
当院では、患者さんの症状を詳しくお伺いし、必要に応じて以下の検査を行います。
- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ): 食道や胃、十二指腸の粘膜の状態を直接観察し、炎症の有無や程度、潰瘍、ポリープ、がんの有無などを確認します。
当院では、患者さんの負担を軽減するため、鼻から挿入する経鼻内視鏡や、鎮静剤を使用した苦痛の少ない内視鏡検査にも対応しております。
眠っている間に検査が終わった、と仰る患者さんも多くいらっしゃいますので、安心して検査を受けていただけます。
内視鏡検査は少し抵抗があるかもしれませんが、正確な診断と適切な治療のためには非常に重要な検査です。
当院では、患者さんの不安を和らげるよう、丁寧な説明と配慮を心がけています。
胃カメラ
逆流性食道炎の治療法
診断の結果、逆流性食道炎と診断された場合、症状の程度や患者さんのライフスタイルに合わせて、いくつかの治療法を組み合わせて行います。
薬による治療
胃酸の分泌を抑える薬や、食道の運動機能を改善する薬などを処方します。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):胃酸の分泌を強力に抑え、食道の炎症を和らげます。
逆流性食道炎の治療において、最も効果的な薬剤の一つです。 - カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB):PPIよりも効果発現が早いとされています。
- H2ブロッカー:PPIよりは作用が穏やかですが、胃酸の分泌を抑えます。
- 消化管運動改善薬:食道のぜん動運動を促し、胃から食道への逆流を防ぎます。
- 粘膜保護剤:食道の粘膜を保護し、炎症を和らげます。
これらの薬を適切に使用することで、多くの患者さんで症状の改善が期待できます。
症状が改善した後も、再発予防のために維持療法が必要になる場合もあります。
生活習慣の改善
薬による治療と並行して、生活習慣の改善は逆流性食道炎の症状を根本から改善するために非常に重要です。
- 食事の工夫
- 脂っこいもの、甘いもの、刺激物を控える:胃酸分泌を促す食品を避けます。
- ゆっくりよく噛んで食べる:消化を助け、胃への負担を減らします。
- 少量ずつ回数を分けて食べる:一度に大量に食べるのを避け、胃の負担を軽減します。
- 食後すぐに横にならない:食後2~3時間は横にならず、重力の力を借りて胃酸の逆流を防ぎます。
- 就寝3時間前までには食事を済ませる:寝る直前の食事は胃酸の逆流を招きやすいです。
- 姿勢の工夫
- 寝る時は上半身を高くする:枕を高くしたり、ベッドの頭側を少し上げるなどして、重力で胃酸が逆流しないようにします。
- 猫背を改善する:姿勢を正すことで、腹圧の上昇を防ぎます。
- 体重管理:肥満気味の方は、体重を減らすことで腹圧が下がり、症状の改善につながります。
- 禁煙・節酒:タバコやアルコールは、下部食道括約筋を緩め、胃酸の分泌を促すため、できるだけ控えるようにしましょう。
- ストレスの軽減:趣味や運動など、ご自身に合った方法でストレスを解消しましょう。
逆流性食道炎でお悩みの方へ
皆様が、安心して消化器の悩みを相談できるクリニックを目指しています。
- 消化器内視鏡専門医による質の高い診療: 当院院長は、長年の経験を持つ消化器内視鏡専門医です。
専門性の高い知識と技術で、正確な診断と適切な治療を提供いたします。
内視鏡検査においても、患者さんの負担を最小限に抑えるよう、細心の注意を払っています。 - 患者さんに寄り添う丁寧な説明: 病状や治療方針について、専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
患者さんが納得し、安心して治療を受けられるよう、疑問や不安にもきめ細やかにお答えします。 - アクセスしやすい立地: 清澄白河駅から徒歩圏内に位置しており、お仕事帰りや買い物ついでにもお立ち寄りいただけます。
- 苦痛の少ない胃カメラ検査: 「胃カメラはつらい」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、当院では患者さんの苦痛を最小限に抑えるため、鎮静剤の使用や経鼻内視鏡にも対応しています。
安心して検査を受けていただけます。
逆流性食道炎に関するよくある質問
Q1. 逆流性食道炎は完治しますか?
逆流性食道炎は、適切な治療と生活習慣の改善によって、症状が改善し、日常生活に支障がない状態を維持できることがほとんどです。
ただし、体質や生活習慣によっては再発することもありますので、定期的な診察と生活習慣の見直しが大切です。
Q2. 市販薬で様子を見ても大丈夫ですか?
一時的な症状緩和にはなるかもしれませんが、自己判断で市販薬を使い続けることはお勧めできません。
症状が長引く場合や、悪化する場合は、重篤な病気が隠れている可能性もありますので、必ず専門医にご相談ください。
Q3. 食事制限は一生続けないといけないですか?
症状が落ち着けば、徐々に食べられるものも増えていきます。
しかし、症状を悪化させる可能性のある食品は、控えめにすることが望ましいです。
ご自身の体調と相談しながら、バランスの取れた食事を心がけましょう。
患者さんへ
逆流性食道炎の症状は、薬物療法で改善に至ることがほとんどです。
胃酸が食道内に逆流すると、食道は炎症を起こします。
この炎症が症状となりますので、胃薬などを用いて長期的に胃酸分泌を抑える必要があります。
院長は消化器病専門医、内視鏡専門医であり、経験豊富ですので、まずはご相談ください。
WEBでのご予約はこちら
参考文献
- 日本消化器病学会「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」
- 厚生労働省「e-ヘルスネット」