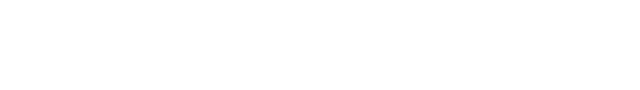潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎とは
潰瘍性大腸炎とは、大腸の最も内側にある「粘膜」という部分に、炎症やただれ(びらん・潰瘍)ができてしまう病気です。
原因はまだ完全には解明されていませんが、免疫機能の異常が関係していると考えられています。
もう一つの代表的な炎症性腸疾患(IBD)であるクローン病と異なり、炎症が大腸に限定して起こること、そして肛門に近い直腸から連続的に奥へと広がっていくことが大きな特徴です。
発症年齢は20代から30代がピークですが、近年では高齢で発症する方も増えています。
病気のタイプ
炎症がどこまで広がっているかによって、主に3つのタイプに分けられます。
直腸炎型
炎症が直腸のみにとどまるタイプ。
左側大腸炎型
直腸から下行結腸(体の左側)まで炎症が広がっているタイプ。
全大腸炎型
大腸全体に炎症が及んでいるタイプ。
主な症状
以下のような症状がみられたら、潰瘍性大腸炎のサインかもしれません。
血便・粘血便
最も多く見られる特徴的な症状です。
便に血や、ドロッとした粘液が混じります。
下痢、軟便
炎症によって大腸が水分を十分に吸収できなくなります。
腹痛
炎症が起きている部分に痛みを感じます。
しぶり腹
何度も便意をもよおすのに、トイレに行っても便が少ししか出なかったり、全く出なかったりする状態です。
便意切迫感
便意をみとめると急速に便が排出されようとするため、時にトイレまで間に合わず漏れてしまうことがある状態です。
全身症状
重症化すると、発熱、体重減少、貧血、倦怠感などが現れることもあります。
潰瘍性大腸炎の診断と検査
上記の症状に心当たりがある場合、まずはIBD専門医に相談することが大切です。
適切な治療を早く始めることが、その後の症状をコントロールする上で非常に重要になります。
当院では、以下の検査を組み合わせて診断を行います。
問診
症状の内容や始まった時期、頻度などを詳しくお伺いします。
血液検査
炎症の程度(CRP値)や貧血の有無などを確認します。
便検査
細菌やウイルスによる感染性腸炎など、他の病気との鑑別のために行います。
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)
潰瘍性大腸炎の診断を確定するために、最も重要な検査です。
肛門から内視鏡を挿入し、大腸粘膜の状態を直接目で見て、「血管が透けて見えなくなっている」「粘膜が赤く腫れている」「出血しやすい」といった特徴的な所見を確認します。
また、炎症の範囲や重症度を正確に把握し、治療方針を決定するためにも不可欠です。
当院では、患者さんの検査に対する不安や苦痛を少しでも和らげるため、鎮静剤(静脈麻酔)を使用し、うとうととリラックスした状態で検査を受けていただける体制を整えています。
安心してご相談ください。
続く血便や下痢をみとめたら、一度IBD専門医にご相談ください。
WEBでのご予約はこちら
潰瘍性大腸炎の治療法
潰瘍性大腸炎の治療目標は、病気を完全に消し去る「完治」ではなく、症状のない穏やかな状態である「寛解(かんかい)」を達成し、それを長く維持することです。
治療の主役は、薬物療法です。
5-ASA製剤(ペンタサ、アサコール、リアルダなど)
治療の基本となる薬です。
腸の炎症を抑える作用があり、軽症から中等症の寛解導入、そして寛解維持のために使用されます。
飲み薬のほか、炎症が直腸やS状結腸に限局している場合には、坐剤や注腸剤といった直接患部に届けるタイプの薬も有効です。
ステロイド
強力な抗炎症作用があり、中等症から重症の患者さんの寛解導入(症状が強い時期)に用いられます。
高い効果が期待できますが、長期使用による副作用のリスクもあるため、症状が改善したら徐々に減量していきます。
当院ではステロイドによる副作用リスクを考慮し、なるべくステロイドに頼らない治療を御提案しています。
経口インテグリン阻害薬(カログラ)
潰瘍性大腸炎では大腸の炎症部位に炎症細胞が侵入し、慢性的な炎症が続きます。
カログラはこの炎症細胞が侵入するのを抑える薬です。
また、効果発現までの時間が比較的短いという特徴もあり、速やかに寛解導入を行いたいときに効果的ですが、価格が高いため導入時は患者さんと相談いたします。
S1P受容体調整薬(ゼポジア)
2025年に潰瘍性大腸炎に対して登場した新しい作用機序の内服製剤です。
抹消リンパ器官にあるリンパ球のS1P受容体に結合し、リンパ球が炎症部位に遊走するのを抑える働きがあります。
この薬は5-ASAやステロイドは無効ですが、生物学的製剤を使用したことがない患者さんに使用すると、比較的短期間でかなり高い効果が持続することが示されています。
一方で、まだ新しい製剤ですので徐脈性不整脈や黄斑浮腫とよばれる副作用のリスクを十分に考慮しながら投与する必要があります。
免疫調節薬(イムラン)
寛解状態を維持するために使用します。
また、生物学的製剤の効果が下がるのを防ぐ目的でも使用します。
生物学的製剤
近年、治療の選択肢として大きく進歩した薬です。
炎症の原因となる特定の物質の働きをピンポイントで抑えることで、高い治療効果が期待できます。
5-ASA製剤やステロイドで無効であった場合に使用します。
生物学的製剤にはいくつか種類があります。
抗TNFα製剤(レミケード、ヒュミラ)や抗IL-23製剤(ステラーラ、オンボー、スキリージ、トレムフィア)、抗インテグリン製剤(エンタイビオ)など患者さんの症状に応じて使い分けを行います。
JAK阻害薬(ジセレカ、リンヴォック、ゼルヤンツ)
これまで、5-ASA製剤やステロイドで無効であった場合には生物学的製剤が使用されてきました。
生物学的製剤は高い効果を示しますが、点滴や皮下注射のように注射針を使って治療を行う必要がありました。
JAK阻害薬は内服で治療を行うメリットがあります。
日常生活の注意点と知っておきたいこと
薬物療法と合わせて、日常生活でいくつか気をつけることで、より良い状態を保つことができます。
食事について
症状が落ち着いている「寛解期」には、基本的に厳しい食事制限はありません。
バランスの良い食事を心がけましょう。
一方、症状が出ている「活動期」には、腸に負担をかける以下のような食品は避けた方が賢明です。
- 脂肪の多い食事: 揚げ物、脂身の多い肉、生クリームなど
- 刺激物: 香辛料(唐辛子など)、炭酸飲料、アルコール
- 消化の悪い食物繊維: ごぼう、きのこ類、海藻類など
ストレスや疲労
過度なストレスや身体的な疲労は、症状を悪化させる引き金になることがあります。
ご自身に合ったリラックス法を見つけ、十分な睡眠と休養を心がけることが大切です。
大腸がんのリスクと定期検査の重要性
残念ながら、潰瘍性大腸炎を長く患っている方は、そうでない方と比べて大腸がんになるリスクが少し高いことが知られています。
しかし、これは定期的な大腸カメラ検査を受けることで、がんやその前段階の病変を早期に発見できることを意味します。
症状が落ち着いていても、主治医から指示された間隔(通常は1年に1回)で必ず大腸カメラ検査を受けましょう。
これが、ご自身の体を守るために最も重要なことです。
知っておきたい「指定難病医療費助成制度」
潰瘍性大腸炎は国の「指定難病」です。
そのため、重症度などの基準を満たして申請・認定されると、医療費の自己負担額の一部が助成されます。
経済的な負担を心配することなく、安心して治療を続けるための大切な制度です。
申請手続きなどでご不明な点があれば、お気軽に当院にご相談ください。
患者さんへ
潰瘍性大腸炎は、病状の波と付き合いながら、生涯にわたって治療を続けていく必要のある病気です。
しかし、適切な治療を受け、ご自身の病気について正しく理解すれば、症状をコントロールし、学業、仕事、結婚、出産といったライフイベントを含め、普通の生活を送ることは十分に可能です。
IBDは如何に長期寛解となるよう治療薬を選定するかが重要です。
当院は日本炎症性腸疾患学会から認定された指導施設です。
IBD専門医である院長が、患者さん一人ひとりのニーズに応じて最適な治療法を御提案します。
お悩みの症状がある方はご相談ください。