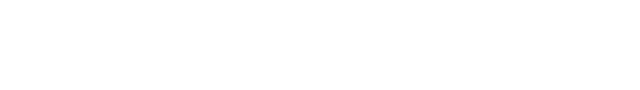クローン病
クローン病とは
クローン病とは、口から食道、胃、小腸、大腸、肛門にいたるまで、消化管のあらゆる場所に炎症や潰瘍(かいよう)ができてしまう病気です。
特に、小腸の終わり部分と大腸の始まり部分に好発することが知られています。
炎症は、一箇所にまとまっているのではなく、健康な部分を挟んで病変が点在する「飛び石状」に現れるのが特徴です。
主に10代から30代の若い世代に発症することが多く、男女差はあまりありません。
原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な要因に、食事や腸内細菌、免疫の異常などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。
クローン病の主な症状
症状は、炎症が起きている場所や程度によって様々です。
消化器の症状
腹痛(特に右下腹部)、下痢、血便、体重減少、食欲不振
全身の症状
発熱、全身の倦怠感、関節の痛み
肛門の症状
クローン病の約半数の方に、痔ろう(じろう)や裂肛(れっこう)といった肛門の病変が見られます。
なかなか治らない痔が、クローン病発見のきっかけになることも少なくありません。
クローン病でよく起こる肛門病変として、skin tagといわれるポリープ状の病変がみられることがあります。
肛門にポリープがある方も注意が必要です。
潰瘍性大腸炎との違い
同じ炎症性腸疾患(IBD)である「潰瘍性大腸炎」と混同されやすいですが、以下のような違いがあります。
| クローン病 | 潰瘍性大腸炎 | |
|---|---|---|
| 炎症の場所 | 口から肛門までの全消化管 | 大腸に限定 |
| 炎症の広がり方 | 粘膜の深い層まで達する | 連続的(つながっている) |
| 炎症の深さ | 粘膜の深い層まで達する | 粘膜の浅い層にとどまる |
これらの違いを正確に診断することが、適切な治療方針を決める上で非常に重要になります。
クローン病の診断に必要な検査
長引く腹痛や下痢などの症状がある場合、まずは専門医に相談し、正確な診断を受けることが何よりも大切です。
当院では、以下の検査を組み合わせて慎重に診断を行います。
問診
いつからどのような症状があるか、食事の状況、ご家族の病歴などを詳しくお伺いします。
血液検査・便検査
貧血や栄養状態、炎症の程度を調べたり、他の感染症でないことを確認したりします。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
診断を確定するために最も重要な検査です。
カメラで直接消化管の粘膜を観察し、クローン病に特徴的な「縦走潰瘍(じゅうそうかいよう)」や「敷石像(しきいしぞう)」といった病変がないかを確認します。
また、組織の一部を採取して病理検査を行うことも可能です。
当院では、患者さんのご負担を少しでも軽減できるよう、鎮静剤(静脈麻酔)を使用して、うとうととリラックスした状態で苦痛なく内視鏡検査を受けていただける体制を整えています。
「検査が怖い」という方も、どうぞ安心してご相談ください。
原因不明の体調不良でお悩みの方は、まずはお話をお聞かせください。
WEBでのご予約はこちら
クローン病との付き合い方 ― 治療の目標と方法
クローン病の治療目標は、まず症状をなくすことです。
炎症を抑えて症状がない穏やかな状態「寛解(かんかい)」を導入し、それをできるだけ長く維持することです。
症状がなくなれば、次に粘膜治癒(ulcer-free)を図ります。
クローン病は症状がなくても大腸粘膜が綺麗でないことが多い疾患です。
大腸内視鏡を定期的に行い、粘膜治癒(ulcer-free)であるかどうかを評価します。
寛解を維持できれば、病気になる前と変わらない生活を送ることが可能です。
治療は主に以下の方法を組み合わせて行います。
栄養療法
腸に負担をかけずに栄養を補給する治療法で、クローン病治療の基本となります。
特に症状が強い「活動期」には、脂肪が少なく消化の良い栄養剤(エレンタールなど)を中心とした食事で、腸を休ませることが重要です。
薬物療法
寛解の導入と維持のために、様々な薬を使用します。
5-ASA製剤(ペンタサなどのメサラジン製剤)
腸管の炎症を抑える基本薬です。
ステロイド
強い炎症を速やかに抑えるために使用しますが、副作用の観点から短期的な使用が原則です。
当院ではステロイドによる副作用をなるべく避けるために、やむを得ずステロイドを使用する場合にはブデゾニド製剤(ゼンタコート)という腸管のみに効いて、全身に作用しにくい製剤を使用しています。
免疫調節薬(イムラン)
寛解状態を維持するために使用します。
また、生物学的製剤の効果が下がるのを防ぐ目的でも使用します。
生物学的製剤
近年、治療の選択肢として大きく進歩した薬です。
炎症の原因となる特定の物質の働きをピンポイントで抑えることで、高い治療効果が期待できます。
5-ASA製剤やステロイドで無効であった場合に積極的に使用することでクローン病の進行を抑えることが明らかとなってきました。
生物学的製剤にはいくつか種類があります。
抗TNFα製剤(レミケード、ヒュミラ)や抗IL-23製剤(ステラーラ、オンボー、スキリージなど)、抗インテグリン製剤(エンタイビオ)など患者さんの症状に応じて使い分けを行います。
JAK阻害薬(リンヴォック)
これまで、5-ASA製剤やステロイドで無効であった場合には生物学的製剤が使用されてきました。
生物学的製剤は高い効果を示しますが、点滴や皮下注射のように注射針を使って治療を行う必要がありました。
JAK阻害薬は内服で治療を行うメリットがあります。
どの治療法を選択するかは、患者さんの病状やライフスタイルに合わせて、相談しながら決定していきます。
日常生活で心がけることと知っておきたい制度
クローン病と診断されたら、日々の生活でいくつか心がけていただきたい点と、ぜひ知っておいてほしい制度があります。
食事について
症状が落ち着いている「寛解期」には、厳しい食事制限はありません。
しかし、脂肪分の多い食事(揚げ物など)や、ごぼう・きのこ類などの消化しにくい食物繊維は、腹痛や下痢を誘発することがあるため、摂りすぎには注意しましょう。
エレンタールとよばれる腸管にやさしい食事と合わせながらバランスの良い食事を基本とし、ご自身の体調と相談しながら食べられるものを見つけていくことが大切です。
生活上の注意点:禁煙は必須です!
喫煙は、クローン病の症状を悪化させる最大の要因であることが分かっています。
治療効果を下げ、再燃のリスクを高めるため、禁煙は必須です。
また、過労やストレスも症状を悪化させるきっかけになります。
十分な睡眠と休養を心がけましょう。
知っておきたい「指定難病医療費助成制度」
クローン病は国の「指定難病」です。
そのため、申請を行い認定されると、医療費の自己負担額の一部が助成されます。
経済的な負担を軽減し、安心して治療を続けるための非常に大切な制度です。
申請手続きなど、分からないことがあればお気軽に当院にご相談ください。
将来のこと
クローン病は若い方に多い病気のため、恋愛や結婚、妊娠、出産など、将来のライフイベントに不安を感じる方も少なくありません。
しかし、寛解を維持していれば、健康な方と変わらず、これらのライフイベントを経験することは十分に可能です。
大切なのは、一人で悩まず、主治医に相談することです。
患者さんへ
クローン病は、長く付き合っていく必要のある病気です。
しかし、それは決して一人で孤独に戦う病気ではありません。
私たち医療者はもちろん、家族や友人、そして同じ病気を持つ仲間たちもいます。
適切な治療を受け、ご自身の病気を正しく理解しコントロールすることで、仕事や学業、趣味や旅行など、あなたらしい人生を歩んでいくことは十分に可能です。
清澄白河ファミリークリニックは、清澄白河駅B1出口から徒歩5分と、アクセスしやすい場所にあります。
日本炎症性腸疾患学会に認定された専門施設であり、院長はIBD専門医・指導医として専門治療を行っています。
クローン病の診断から治療、そして日々の生活や将来の不安に関するご相談まで、患者さん一人ひとりに寄り添い、二人三脚で歩んでいくパートナーでありたいと願っています。
原因不明の体調不良でお悩みの方、クローン病と診断され不安を抱えている方、まずは私たちにそのお話を聞かせてください。